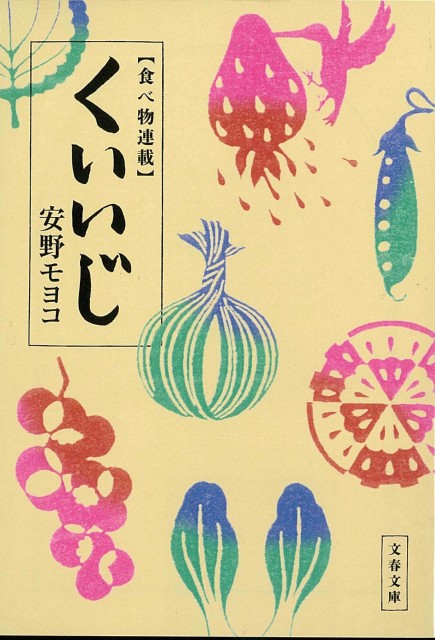食べられない(食べ物エッセイ『くいいじ』より)
事務所に出勤すると机の上に四角くて美味しそうな物が置いてあった。
白い小さなチーズケーキかと思って手に取ると石鹼で、あと一息でかじろうとしていた私はちょっとがっかりして しまった。
こんな美味しそうな石鹼を作るとは…。
さすがLUSHだ。
手造り石鹼で一躍有名になったこのお店は素材に植物や自然由来の物を使うのだが今回の新作は豆腐、お米、日本 酒で作ったものだと言う。
食べたくなるのも無理は無い。
あきらかに美味しい物で出来ている。
包み紙をじっと見ると当然と言うか
「本品は食べられません」
と明記してある。
今は他に食べる物が有るから手を出さないけれど、雪山で遭難したりエレベーターに閉じこめられて四日間、とか言う状況になったら絶対食べるだろうなと思った。
子供の頃石鹼は食べなかったけれどフルーツ味の歯みがき粉と言うものを半分食べていた。
「半分」と言うのはどう言う事か、と言うとさすがに歯みがき粉が食品でないと言う事ぐらいは把握して居るのでいきなり正面切って食べるのははばかられる。
しかしながらバナナ味だイチゴ味だと甘いフレーバーを漂わせている半透明のペーストは、一瞬目をつむってしまえばお菓子のような物である。
そこで、歯をみがきながらなんとなく食べていくのだった。
大人になってみれば、どんな味だろうと歯みがき粉を食べるなんてまっぴらゴメンだが、子供で更にバカだったので
「うっすら食べ物じゃないかも知れないと思いつつ食べちゃいました!!」
みたいなラインを狙っていたと思われる。
人に話してみたら皆割と同じで、やっぱり子供はみんなバカだとホッとしたのだが、中にはチューブからいきなり吸ってたりベロベロ舐めていたと言う人も多くて、自分は歯みがき粉食いとして甘かったと思い知らされたのであった。
他にも小学生時代に食べそうになっていた物がある。
うっすら食べ物じゃ無いと思っていたどころか完全に食べ物じゃ無いとわかっているにもかかわらず食べたくて仕方無いもの。
それは又しても果物フレーバーやお菓子フレーバーの付いた消しゴムであった。
消しゴムはどう考えても食べ物で無い上に、ゴマ化しつつ口に入れたとて嚙んだり飲んだりするのは困難なシロモノである。
それがわかっていながらも時々筆箱からそっと取り出しては
「もしかして…」
と言う希望と共にちょっと嚙んでみたり、その度に
「やっぱり食べられなかったか」
と軽く失望してみたりして居た。
どうして食べられないとわかっている物を食べようと思うのだろうか。
単純に食べ物の香りが付いてるからなのだろうか。
どうも違う気がする。
本来食べられない物質が食べられる物に変化するかも知れない、というファンタジックな期待がそこには有った様に思う。
石を食べてる人とか紙を食べてる人とかねんどを食べてる人とか、子供の時はよく周辺に居たものだが彼らはどうだったのだろうか。
単純に味を愛していたのだろうか。
歯応えを?
小学一年の時、隣の席の男子が細長くしたねんどを半分ほど食べて先生に取り押えられ、私は気分が悪くなって廊下の流し場で吐いてしまったが、人の居ない授業中の廊下にボトリと落ちていた食べかけのねんどを今でもありありと思い出す。
彼などは
「食べられない物が食品に変化する」
と言う想像など一足とびにいきなり食べていたのだから、脳の中で勝手に変換が行われていたのかも知れない。
大人になって食べられない物を食べる幻想は持たなくなったが、食べられる物を別の用途で使うようになった。
蜂蜜をリップグロスとして使用するのである。
オリーブオイルでメイクを落とす事もあればお酢をリンスにしたりもする。
特に蜂蜜は小さなびんに入れて持ち歩いているので、エレベーターに閉じ込められてもこれでしばらくは生き延びられるはずである。
それにしても、なんでこんなにいつもエレベーターに閉じ込められる事を心配しているのかわからない。
しかしながらそんな閉鎖空間の中で自分の持ち物をチェックするとしたら、まず何を食べられるかだ。
消しゴムと石鹼と歯みがき粉だったら…。
やはり石鹼より歯みがき粉だろうか。
どれも持ち歩いてはいないけど。